![]() ちょっとした話 MEMOないでアップした小説を 見やすくするためにここで紹介します。
ちょっとした話 MEMOないでアップした小説を 見やすくするためにここで紹介します。
それぞれの話のコメントなどはMEMOをご覧ください!
| 7月17日 ブレイブストーリーのネタバレSSです。 |
| 「ねえ!美鶴!」 三谷 亘(みたに わたる)は、学校の下校中に自分の前を歩く芦川 美鶴(あしかわ みつる)を呼び止めるが、とうの美鶴は振り返ることなく、さっさと足早に歩いていった。 「美鶴!」 再度、呼び止めても美鶴は振り返らない。 仏の顔も三度、という言葉があるが、亘もとうとう痺れを切らす。 「美鶴!」 スピードを上げて小走りで、美鶴の前に回りこんだ。 「…なんだい、三谷…?」 肩をつかまれた美鶴は、ようやく亘の方に顔を向けた。 美鶴の顔立ちはどの同級生と比較しても、端正で整っていて亘は何度も見ているはずなのに、そのたびに一瞬だけど、魅入ってしまうのだった。 でも、その顔で、自分を「三谷」と呼ぶ。 「何で、僕のこと、名前で呼んでくれないの?」 亘は、ずっと思っていた事をいきなり切り出した。 ☆ 幻界(ヴィジョン)から戻ってきて、奇跡的な再会を果たしてから、僕たちは絶対無二の親友になるって、亘はそう思っていた。 でも、美鶴は最初出会った時と同じ様に、いや、むしろその時よりそっけなくなっていた。 亘はそれが、不思議でならなかった。 − また逢えて嬉しかったのは、僕だけだったの? そう何度も思って、問いただそうとしたが、その度にするりとかわされた。話をしようと、隣のクラスに顔を出しても返って来るのは「もう帰ったよ」というクラスメートの言葉ばかりだった。 だから、今日こそは問いただそうと思った。 担任の先生が、ちょうど用事があって終わりの会がなかったから、今日がチャンスだって。 校門の前で、美鶴を待ち伏せした。 チャイムのすぐあとに、美鶴が妹のアヤをつれてきた。片手をつなぎ優しそうに微笑む美鶴。 − そんな顔できるんだね…? 亘は、遠めに美鶴を確認してそう思った。廊下でたまたますれ違っても、目をそらしてそそくさと立ち去ってしまう美鶴。 「ねえ。美鶴…」 心の奥に不快を隠して、声をかけた。その声に、驚いて美鶴は顔を上げた。 「わ…」 美鶴は、しまったとばかりに口を手で覆い、それから妹のアヤに一言声をかけて、足早に亘の前を通り過ぎた。 ☆ 「ねえ、何で、僕のこと避けるの?そして、亘って呼んでくれないの?」 「…」 肩をつかまれたまま、美鶴は黙ったままだった。 「運命の塔で、呼んでくれたじゃない…亘って」 それでも美鶴は黙ったままだ。 「ねえ、変な友達って僕のこと?」 亘は、思い切って別の事を聞いた。 「え…?」 「あの、女の子、ゾフィ…だっけ。闇の宝玉のところであった女の子が、言ったんだよ?」 「…なんて」 さっきまで、黙ったままだった美鶴がようやく話に乗ってきた。でもそれは、会話を楽しむなんてレベルではなく、ただ、これからの内容を確認したいだけ、そんなことがあからさまな表情と態度だったが、それでも亘は久しぶりに美鶴と会話できたことが嬉しかった。 「『美鶴様の友達ってあなたですよね。すぐにわかりました。美鶴様を助けてくださいって』そういってた。」 「…」 「俺のこと、友達って話してくれたんだ…ってそれが嬉しかった。」 一方的に話す亘だったが、美鶴は下を向いたままだった。 「ねえ、何でそれで避けるの?僕たち友達でしょ?」 亘は、ひざを曲げて美鶴の視界に入り込んだ。 すると、そこには。顔を真っ赤にした美鶴がいた。 「…あれ?なんで…?」 「う、うるさい!」 とうとう、美鶴は肩にかけられていた手を振り払った。そして、数歩、亘から離れるように歩き出した。 「あ、待ってよ!」 亘は、思わず腕を掴んだ。 「離せよ!」 激しい言葉の割には、振り返った美鶴の顔は… 「何で、そんなに顔真っ赤なの?」 亘は、思わず見たままを言ってしまった。 美鶴は今度こそ、何も言わずに腕を振り払って、走り出した。美鶴の顔に驚いて力を抜いてしまったせいか、あっさりと振りほどかれてしまったのだ。 「なんで?美鶴は照れてるのかな?」 美鶴が照れていた理由。 そして、亘が美鶴にこだわる理由。 それぞれの理由に、気付くには二人ともちょっとまだ幼すぎた。 でも、二人の時間はこれからだ。二人の前には沢山の時間がある。 二人はこれから…。 |
| 11月18日 |
| あなたのもとに…戻って来ていいですか。いつの日か。 それは。今ではない。もうちょっと時を隔てて。 生き返りなんて…今まで信じてなかったけど、今は信じてみたい。あなたにもう一度会うために。 鳥でもいいかな?あなたの肩にそっと、ふわりと舞い降りる鳥。そして、あなたの髪に軽くじゃれてみたり。 あなたの、足にまとわりつく、犬や猫でも。そして、眠るあなたの布団にもぐりこむんだ。あなたを暖めてあげる。そっと。 それとも。大樹でもいいかな?一息ついたあなたが心地よく休めるように、木陰を作ってあげるから。 いろいろ考えてみた。でも。やっぱり人がいいな。 また、人に生まれてきたい。 だって、言いたいんだよ。 「ただいま」 って。 その言葉を あなたに言いたい。また、あなたに出会いたい。お願い。それ以外は望まないから。 僕の手からすり抜けて行く、あなたに手を伸ばす。届かないってわかっていても。 あなたのもとへ。 あなたのもとに。 |
| 11月17日 |
| 「僕」は今までひとりだった。 寂しいとか、そんなことなく。それが当たり前だった。 ひろい、ひろい、縦も横もない真っ白な空間に。 僕はいた。扉の前のの形のない「僕」がいる。 それが当たり前だった。 「僕」の前に現れた、その体。 その体には…もちろん、魂も精神もなくて…ただ、体が転がっていた。 「もう一人の僕」が…この扉に近づく為に得た代償としてここに置いていった。 抜け殻となったその「もう一人の僕」に「僕」はそっと近づいた。空気のように、形のなかった僕がその瞬間、「もう一人の僕」と「僕」一緒になった。 肉体という…カタチを得て、「僕」がこの中に物質として存在するようになって…「僕」は今までひとりだった事を…痛感した。 心 がないはずなのに、体に染み付いた、「誰か」への想い。手を必死に伸ばそうとする衝動に突き動かされそうになる。 「会いたい」 その気持ちは誰に対するものなのか…「会いたい」という気持ちゆえに…自分が今一人である事を痛感する。思い知らされる。 時々「僕たち」の前に現れては消える、もうひとつの扉と、何かの影。今まで、ありえない不協和音が、今は心地よい。 そんな中、突然現れた、もうひとつの不協和音。「僕たち」に差し伸ばされた手… (ああ、僕が望んでいた手はこの手なんだ…) でも「君」は「もうひとりの僕」じゃない。 『君はボクの魂じゃない』 心の中に潜むもう一人の僕が 手を伸ばす。あの人に。その心にひきづられ、僕も扉をくぐってしまいたくなる。「君」と一緒に。 (ひとりにしないで!) ひとりなんて、一人ぼっちなんてそれが当たり前だったのに…思わずそんな感情が心に生まれてくる。 当たり前の「僕」の周囲が崩れる音がする。 (その手を取ってしまったら…「僕」は一人じゃなくなるの?もうここにいなくてもいいの?) そんな、僕が本来考えるはずのない感情が浮かんでくる。 でも、「僕」は行けない。ここでしか「僕」は存在できない。 あなたが手を差し伸べたの相手は「僕」でなくて「もう一人の僕」だ。 ありがとう。「僕」を必要としてくれて。それが偽りでも。 『一緒に行けない』 いつか、「もう一人の僕」が、ここに来たら。ちゃんと、この体を返すから。わがまま言わずに返すから。 その時には僕も連れていって。全部とはいわないから、この体に残っていた、魂の一部のように、「僕」の一部を。 「もう一人の僕」に託すから。 その時がやってくるそのときまで、まだ、もうちょっと迎えが来るまで。もうちょっと「僕」でいさせて。もうちょっとだけ… |
| 11月13日 |
| エルリック兄弟が、旅をしているとき。エドワードは弟アルに向かって…贖罪をするように、つぶやいた
「俺はあいつから…奪ってしまったんだよ…ふとした出来心からさ…」 辛辣な表情で続ける 「アルフォンス…お前…どうして、りんごは擦りおろしてばっかりなんだよ…?男なら豪快に、かみつけよ!」 「え・・・?この方がおいしいじゃないですか?」 「…そんなにシャカシャカ擦ってんじゃないよ!お釈迦様になるぞ!」 「…ああ、あの東国の宗教思想ですか?僕はクリスチャンだから大丈夫です。」 …と擦りおろす手を止めずにハイデリヒはにっこりと答える。エドワードにだって嗜好の問題って言うのはわかっている。でもなんとなく我慢ならないんだ。 すりりんごは・・・確かにうまい。それは認める。でも、それは風邪を引いたときにお母さんが、作ってくれるもんであって…ああ、うまい言葉が思いつかない! 自分の食べ方を真っ向から否定されているようで…。自分と同じ行動をしろとは言わないが…、たまには食べ方を変えろよ!俺と同じにしてみろよ!!って。 「りんごはこうやって食えよ!歯茎の病気だって!すぐわかるぜ!」 とハイデリヒに向かって、デモンストレーションをしてみるも… 「僕には…そんな、豪快な食べ方はできないな…」 と…言いながら、目配せをした。その行動が…エドワードにとっては…なんとなく馬鹿にされたような気がした。下品だなあ…って、なんとなく見下されたような…。 なので思わずエドワードは言ってしまった。 「アルフォンス…すりりんごばっかり食べてると…噛む力が低下して…若はげになる確率が高くなるんだ…って知ってるか…?」 「え…?」 ハイデリヒは、その言葉を聴いた瞬間…この世の終わりような顔をして…そして、さらを取り落とす… そして、それ以後…ハイデリヒがすりりんごどころか…りんごそのものを食べることなく…逝ってしまった… 「アル…俺は…あいつから…奪ってしまったんだよ・・・・あいつから…りんごを!」 |
| 10月25日 |
| 「…なんでこうも…」 ハイデリヒは書類の束を持ちながら…いや握りつぶしそうになりながら… 「誤字脱字が多いんですか!!!!」 握り締めた拳でテーブルをたたきつける。その反動でコーヒーカップが一瞬中に浮く。しかし、中身はかろうじてこぼれることなく、その場にとどまった。 「あなたって人は…。何でこんなにすごい内容の論文書くのに…ど、どうして…」 今度は、涙を流しそうな勢いで。 「何でこんな子供が間違うようなスペルミスをするんですか!」 提出論文の仕上がりを、いつものようにハイデリヒにチェックしてもらっていたエドワード。そのつど、誤字が多いと、それは数え切れないほど指摘されていたのだが…。今回ばかりは雷が落ちた。 「だってよお…」 エドワードが思わずペンの先を額に当てながら、言い訳をしようとする。 「だってがなんですか?いくらあなたがドイツ語がFirst Languageでないのはわかっていますよ。でもそれでもこれは酷すぎます。何で、技術系の専門用語の単語は何一つとして間違えないくせに、小学生でさえ間違えないような単語のスペルミスをするんですか!」 どんどん大きくなってくるハイデリヒの声に、思わず耳を塞ごうとする。 「そこ!今日という今日はちゃんと聞いてもらいますからね!」 要するに。エドワードは、あっという間にドイツ語をマスターした。そのマスターの方法はいきなり専門書を読んで、単語と文法を叩き込んだかなりの荒治療。根本的に頭のつくりが違うエドワードだからできる手法ではあるが、これがひとつの弊害を生んでいた。エドワードは興味ある専門領域の単語やらは一発で覚えてしまうのであるが、そうでない単語などは、何度聞いても右から左に抜けてしまうのだ。その忘れ去られてしまう対象は、本当に日常的なもの。普通に使われる単語の数々。それらがどうしても抜けてしまうのだ。実際女性名詞、男性名詞など慣れで無意識に使い分けてしまう類のものであるので、ドイツに来て1年弱のエドワードにそれを求めるのは間違っているのかもしれない…が、ハイデリヒにはどうしても納得できないのである。 「何で、こんな長い単語を一度も間違えないくせに…どうして…」 先ほどと同じ内容を繰り返す。エドワードだって、何度も言われいるので、間違えないようにとは思っている…のだが、どうしても文章をどうまとめるかという命題に気を取られてしまう。つまり、意識はしているが、優先順位がどんどん下がっていくのだ。 「でもなあ、それに気をつけていると、どうしても論文が書き進まないんだよな…」 言い訳にしか過ぎないのは、わかっているが、ついひとこと。 「でもも、ストもありません!まったく…」 どうして、こんな接頭語を…などとぶつぶつと。スペルミスが多いのはわかっているからこそ、こうやってハイデリヒに確認を頼んでいるのであって。その結果、小言を言われるだけの原因が自分にあるのは充分に承知している。 しかし。こうもぶつぶつと、同じ事を何度も何度も何度も何度も…言われるとさすがに、腹が立ってくる。自分に原因があったとしても、それはそれ、これはこれ。 「五月蝿い!黙れ!」 「はい?」 依頼しておいて、この態度は一体何様のつもりだ?エドワード様か…と、ハイデリヒは妙に納得してしまうが…。 「エドワードさん…あなたって人は…!」 わなわなとハイデリヒの体が小さく震えている。 「…」 このままだと、ハイデリヒはまた五月蝿く程くらいついてくるだろう。黙らせるにはこれしかないだろうとエドワードは頭の中で瞬時に考えをめぐらす。 「エドワードさん聞いてるん…!で…」 言葉が言い終わらないうちに、エドワードはハイデリヒの胸倉を掴み引き寄せる。そして軽いキス。 「…」 ハイデリヒがようやく黙るのを見届けてから 「確認よろしく頼むな。」 と、微笑をたたえつつ、一言残して部屋に戻る。次に書きたい挙げたい論文は頭の中でほぼできている。あとは文に起こすだけである。 「あ、悪魔だ…」 ここまで尽くさせておいて…自分が都合が悪い時には、あっさりと身を翻して逃げるエドワードのその様を見てハイデリヒは、今度は小さく一言つぶやいた。 悪魔に魅入られた天使はいつも開放して欲しいと文句を言う。でも逃げる隙はあるのに、逃げない。悪魔は天使を独占して、天使は悪魔に独占されるそんな魅惑な麻薬のような喜びを…当の本人たちはまだ気付いてない。 |
| 10月25日 |
| それは 木漏れ日がさす昼下がり。 悩めるロイ・マスタング大佐は腕組みをしながら歩いていた。 「…」 今日の昼食はなんにしよう、そんなくだらないことではない。 小判鮫がごとくについて回るクールビューティからどう逃げようか、そんなことではない。それに関しては、とっくに諦めている。逃げようがないと。 さて、悩める青年の悩みとは… 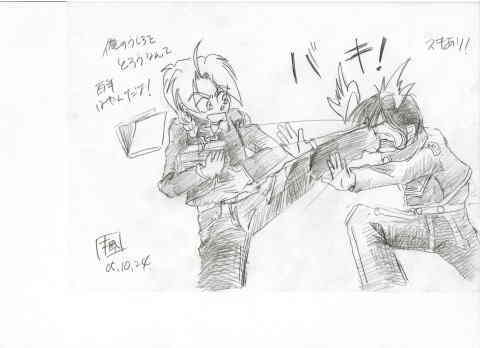 ふと見上げると、その当人を見つけた。 重そうな書物を何冊も…身長に見合わない…などといたら失礼だろう? こんなにも自分が心を悩ませているのに、その本人は露とも気付いてない。そう思うとなんとなくむしゃくしゃしてきた。 よし! たまには驚く顔を見せてもらおう!と。 「隙あり!」 その背後から飛び掛ろうと…した矢先 バキッ!!!! 「オレの後ろをとろうなんて百年早いんだよ!」 顔面に感じる痛み。 周り蹴りのクリーンヒット。 そして、彼は何事もなかったの用に去っていった。 執務室を不在にしている…いや、正しい表現ではない。 ホークアイ中尉が、遅れがちの書類を采配をしている間に とりあえずできている書類だけでも、と 将軍に届けに行っている間に、逃亡を無事に果たした その本人を。 「…」 握られた書類に一部皺が寄る。 きわめて冷静を装っているが、内心は相当腹を立てている顔だ、彼女をよく知っている人が見ればそう答えるであろう。 「…」 こつこつと普段はたたないように歩く彼女の靴音が響く。 時々立ち止まっては周囲を見回す。そして歩き出す。 何処を探すか、思案しているようにも見えるが、それはその表情から察することはできない。 ふと、顔を挙げ一点を見つめる。 そして、先ほどよりさらに大きな足音を立てて、大きく手を振ってその目的に近づく。 「そこにいらしたんですね…?大佐?」 優しく、でも地の底から響くような中尉の台詞。 いつもなら「悪い…中尉」とでも謝罪の言葉でも返ってくるのだが。どうやっても頭が上がらない大佐の常套手段である。 …が、その当人は壁をむいたまま手をついてうずくまっている。 「大佐!聞いておられるのですか?」 反応が鈍い、本来は敬愛すべき上官に痺れを切らす。 「あなたはやるべきことがわかっていらっしゃるのですか?」 さらに追加して責め立てる。 「…わかりました。ではそのままでお話をお聞きください」 中尉も長い間彼の下で働いていたわけではない。何か事情があるのだと、鋭く察した。 「まず、絶対に今日中に確認してもらわないといけない書類を読み上げます。こちらにはサインだけでなく、東方司令部責任者としての…」 有能な部下は、必要と思われる事を効率よく読み上げてゆく。それに対してロイは背中を向けてうずくまってはいるが、適度に頷いて答える。 「…以上です。私は連絡室で待機しておりますので、以上の書類が仕上がりましたらご連絡をお願いします」 「…わかった。すまない中尉…」 そう小さくロイは背中で答える。 「…大丈夫ですよ。」 ようやく、優しい微笑むような声で答える。 「あ、エドワード君」 「え」 と思わず立ち上がって振り向くロイ・マスタング すると、当のエドワードではなく、自分の部下が目の前にいた。 「何処だ、エドワードは?」 「…嘘です」 「…は?」 ホークアイが見たものは、敬愛すべき自分の上官の顔に くっきりと残った足跡 。よくここまで、足跡が…と感心した中尉だった。 「大佐。しばらく人はいませんので今のうちに 執務室にお帰りになった方がいいと思いますよ? それでしばらく書類の整理をされているうちに 消えると思いますので、よろしくお願いします。」 この段になって、ロイはハメられたことにようやく気付いた。そして目の前にいる相手が、一枚も二枚も上手である事を。 「…ご忠告、受け止めておくよ」 「ではよろしくお願いします」 中尉はそう一言残すと、踵を返して連絡室に向かっていった。 ロイはやれやれと、手で顔を隠しつつ、周りを気にしながら 執務室に向かうのであった。 |
| 10月22日 |
| (映画後 生身の兄弟で) 「…おい、アル。地震か?」 論文書を広げていたが、エドワードが顔を上げて、台所で料理を作っていた弟アルフォンスに問いかける。 「え?僕には感じないけどなあ…」 と、天井から下がっている電灯を見上げる。電灯なんて普段じっくり見ることはないものだが、自身の時には注目の的であり、誰もが見上げて、その動きを観察する。 電灯は微動足りともしていない。 「…兄さん…?地震じゃないみたいだよ?」 電灯を確認したうえでエドワードに、改めて返事をしてみる。 「おかしいな?確かに揺れたと思ったんだけど…?」 首をかしげるエドワード。 「兄さん…ちょっと。」 アルは自分の前髪をかきあげておでこをさらす。次に、右手でエドワードの前髪を同じようにかきあげる。 こつん アルは自分のおでこをエドワードの御でこに当てる。 「…に、兄さん、こんなに熱あるのに?どうして平気な顔してるのさ!」 額が合わさった瞬間、伝わった体温と言うか、どう考えても人間のツ上の体温とは考えられないほどの熱源に驚きを隠せなかった。 「……へ?」 発熱しているエドワード地震がその言葉に驚いた。 「お、オレ熱があるのか?」 「決まってるでしょ、兄さんすごい熱だよ!」 その後のエドワードの発言は全て、かき消される。ベッドに強制連行。 ベッドに横になってみれば、確かにだるさを自覚する。頭を起こすのさえ億劫に感じている自分をようやく自覚したエドワードだった。 最近寝不足だったからな…と原因についていろいろ予想してみたが、結局はそれしかないと、自己管理を怠った自分を振り返ってみる。 「…氷もらってきた!大丈夫?兄さん?」 皮袋に大切に入れられた氷と洗面器を抱えて、アルが部屋に戻ってきた。 「大丈夫〜!」 エドワードは弟を心配させるまいと、あえて元気そうな声を出すが、一度自覚してしまった発熱を完全に隠すことはできない。やはり語尾にいつものような覇気が無い。 「…」 それを聞いてアルは、一気に涙を流す。 「ど、どうしたんだよ?」 弟の異変に、動揺してすぐさま傍に駆けつけようとするが、思うように動かない自分の体。 なので、その替わりにこいこい、と手招きをしてアルを呼び寄せる。濡れた瞳で、それを確認してアルはエドワードの傍に近寄る。 「何?何か欲しいものあるの?兄さん?」 手招きをした手を握り、要求を聞いてくる。 「違う、違う、何で泣いてんの?お前?風邪ひいてるのはオレだぜ?」 困ったような表情で、空いた手でアルの頭を軽くなでる。 「…だって、そんな熱がね兄さんでてるのに…僕気付かなかったんだもん…」 とうとう、布団に突っ伏して泣き出してしまう。 まったく、変な所で自分に責任感じるんだよな?エドワードはそんな弟を見て苦笑する。 いつだってエドワードの体調を気遣う。その理由として「兄さんは自分の体調管理に気を配らないからだよ」と。だからこそ、自分の事以上にエドワードの体調管理を行っているのに、病気なんかすると自分よりアルが落ち込んでしまうので、いつもは気をつけていたのだが、今回は論文を読み込んでいてうっかり睡眠不足になってしまったのだ。 「ごめん、兄さん・・・僕が止めればよかった…」 アルは溢れる涙を止めようとはしなかった。 エドワードは気付いていたのだ。それが弟の代償行為である事を。今まで一緒にいられなかった2年間。そして、開いてしまった肉体上での年齢差。今までひとつだった魂が、二つになった虚脱感、そんなことであろう。 その空間を埋めるかのように、アルはエドワードの事を自分のことのように考える。それがわかっていたのであえてエドワードはそれを是正しない。アルのその行動に付き合う。 「ごめんなアル。俺自身も気付かなかった」 髪を優しくなでる手を止めて、つむじにそっとキスをする。 その優しい感触に、アルはようやく静かになる。 (どうして俺たちは「ふたり」なんだろうな…?) 弟の神を優しくなでながら…ふとそんな事を思った。 |
| 10月18日 |
| 「なあ、何でオレのこと。エドワードって呼ばねえの?」 有無を言わさず、強引にエドワードさんが割り込んできて数日後。こんな事を彼は言った。 「…だって、年上ですしね…?」 多少困った顔してハイデリヒは答える。 「別にいいじゃん、みんな俺のことそう呼んでるぞ?」 何の気なしにそういう。 (まったく簡単に言いますね…) 見えないように、思わずため息をつく。 (なんだってこの人は無意識に僕の心を試すような事を言うんだか。) ハイデリヒの母方の実家は由緒あるフォンブラウン伯爵家。その関係で、作法や行儀見習いなどは幼い頃から徹底的に叩き込まれいてる。もちろん相手を敬う方法も。だから、こんな事を言われると、今までの自分の価値観とか、そんなことが覆されるような気がするのだ。 「別にいいじゃないですか?『エドワードさん』でも」 (何でそんなにこだわるのだろうか?この人は。正直そう思う。名前なんて、人を認識する為の番号にしか過ぎないだろう?そうだよ。だからなんで?) 礼儀作法が徹底している彼にとって、相手を個人として認め尊重する為の方法としてちゃんと相手の名前を呼ぶ、これは常識である。 「…でも、俺がそう呼べって言ってもか?」 エドワードはいつの間にか近くまで寄ってきて上目遣いでハイデリヒを見上げる。その仕草になにやら艶かしいものが一瞬思考の隅を通り過ぎたが、あえて気付かないようにする。 「そんな呼び方を変えて欲しいなら…呼んであげますよ?Herrエルリック」 本当はそんな呼び方なんてしたくないのに。でも話題をそらす為に、ついはぐらかしてしまう。 「お前のそういうところが気に食わないんだよ!」 突然そんな事をエドワードは掴みかからんがばかりに、にじり寄ってくる。 「…え?」 適度に交わすつもりでいったその言葉にどうしてそこまで反応するのか?ハイデリヒは顔ひとつ分からにらまれる視線に困惑していた。 「お前は、そうやって、オレを距離を取ろうとしている。なんでだよ?」 まっすぐに瞳を向けて、胸襟を掴みエドワードは訴える。 「え・・・?」 「育ちがいいのか分からないが、そうやってすました態度が…気に入らない!」 そんなつもりはないのだが、ハイデリヒが言おうとするが、いえるような雰囲気ではなく。 「オレは…そんな育ちのいい奴なんか…お前の口からそんな仰々しく呼ばれると…!」 「ええと。僕はどうしたらいいんでしょうか?」 収拾がつかなくなりそうなので思わず、言ってしまったとぼけた質問。その言葉に我にかえるエドワードだった。 「…すまん取り乱した。お前にはお前の過去があるんだもんな、いきなり言われたって困るよな」 胸倉を掴んでいた腕を放し、呼吸を整えつつエドワードは自身を取り戻した。 「ありがとうございます」 なんとなく気まずい空気が流れる。 「…それで…僕はどうしたらいいでしょうか?」 思い出したようにハイデリヒは改めて問いかける…。 「…善処してくれよ?すぐにとは言わないから、丁寧に呼ばれると、なんか虫唾が走る」 いつもの表情に戻ってエドワードは答える。 「頑張りますよ、でももうちょっと待っててください。あ、誰か来たようですね?」 入り口のノック音を確認しようと、エドワードに背を向けたとき。何かが聴こえた。 「あれ、何か言いましたか?エドワードさん」 いったん立ち止まって振り向く。 「なんでもない、早く行けよ待たせちゃ悪い。」 「はいわかりました。」 そう言って、玄関に向かう彼を見送って。それからもう一度つぶやく。今度は彼に聴こえないように。 「お前のその顔で、その声で。俺を他人行儀で呼ぶのは…これが一番俺に課せられた地獄なのかな…?」 皮肉めいた、自分を責める表情で、誰にも聞こえることない独り言をつぶやいた。 |
| 10月14日 |
| 「アル…」 隣で眠るエドワードが寝言でつぶやいた。それをしっかりと聞いてしまったハイデリヒ。 … 自分の名前…のはずだけど、その響きは自分を指すわけではない。それがわかっているから、本当に面白くない。まじまじとエドワードの顔を覗き込む。 (…まったくなんて幸せそうな顔をしているんですか…?) 人の夢なんて覗き込むことはできないけど、明らかにこれはわかる。弟さんと仲良く楽しんでいる夢をみている。 (…まあ、兄弟の絆に入り込むことなんて…できないですしね…) わかっているけど…やっぱり面白くないのである。 (…) そっと眠るエドワードの耳元にそっと口を近づける 「…そこにハイデリヒが現れた。彼は弟さんを置いて、こっちに来るように手招きしている…」 エドワードを起こさないように、やさしく、でも夢の中の彼の心に届くように、そっと囁く。 「…うう〜ん?あ、リヒ…?」 こちらを向かって寝返りを打つ。 「さて、刷り込み完了!」とそれを確認して、ハイデリヒは安心したように、かけ布団をかけなおして眠りにつく。 翌朝 「おはよう、エドワードさん」 いつもどおり早く起きて、コーヒーの準備を整える。エドワードの好きなちょっと薄め。その香りがほのかに部屋中に満ちる頃。いつもと同じようにドアが開く。いつものように眠そうな表情で、リビングにやってくる。 いつもは。寝ぼけ眼でもおはようって挨拶を返すのに。今日はそれがない。ハイデリヒをみてわざとらしく目をそらす。 「どうしたの?なんか変な夢でもみたの?」 さり気に訊ねる。 「…」 エドワードは無造作にハイデリヒが用意したコーヒーカップを取り上げ口をつける。 「ねえ?エドワードさん。どんな夢見たの?」 黙っているエドワード わざと話をしない彼の姿を見て、ハイデリヒは作戦の成功を確信する。それ以上は何も言わない。言う必要がない空間があった。 |
| 10月4日 |
| 「神を継ぐ少女」 最後の戦い 「ア、アル???ど、どこだ?」 常に自分の視線の中にあったその姿が消えた。 ソフィを助ける為に、ヴェルザを再度封印する為に、乗り込んだ神殿。踏み入れた瞬間、首筋に鋭利なナイフ突きつけられたような凍る感覚…そして射殺せるほどの視線を感じた。 身体は拒否をする。本能が心の奥で叫ぶ。 これ以上は入るな。 そう何度も自分に忠告する。少しでも油断すると自分の意思とは無関係に、後退する事を願う自分の足。背中を伝う冷や汗にさえ、恐怖を感じる。 逃げたい。そう思った気持ちを隠すことはできない。 「兄さん…行くんでしょ?助ける為に。」 そんな自分の気持ちを感じているはずなのに。相棒は自分を励まさない。前に進む為の言葉を自分に投げかける。たった一つの言葉なのに。その言葉が自分の奥に生まれた弱い心を…溶かしていく。 エドは一呼吸置いて。アルフォンスの冷たいけれど、暖かく感じるその鎧に触れる。 「…行くか。」 「そうだね、兄さん。でもここらかはもう戻れないみたいだね。もう一度聞くよ。今の僕たちには二つの道がある。このまま何も見なかった振りをして、ここから出て行く。もうひとつは…ともすると、命の危険だってある。どうする?」 控えの間の起動スイッチに突っ込もうとするエドワードをアルフォンスは引き止める。 「…確かにその方法もあるな。でも。ここで逃げたら…俺たちは一生…近づけない…そう思う。人間、逃げること必要だけど…今はその時じゃない…。行くぜ。アル」 「行こうか。僕が絶対に守ってみせるよ。」 中身がないはずの、アルの鎧の瞳が瞬きしたような気がした。でもそれをじっくり見るときではない。全てが終わってから。 行くぞ。 エドは左の赤いスイッチを。アルが右の青いスイッチを。同時に掛け声をかけて押す。 すると、仕掛けられた罠は…お互いの姿をかき消す。 「ア、アル!!」 「兄さん!!!」 |
| 10月3日 |
| 「美味しそうな場所って何処だろう…?」 少し遠出をしたアルフォンス・ハイデリヒが自宅で待つエドワードに、帰りが遅くなりそうだから夕食は外食で済ませましょう、出て来れませんか?と電話をしたのは1時間前。 「わかった。そうだな、お前今何処?そこなら…あ、セントラルタウンの中央広場の…ガーゴイルの像があるだろ?あの近くの…そうだな、『美味しい所で』待ってるよ。」 そう電話でエドワードは伝えてきた。え、それは何処?と詳細を聞こうとするが、彼らしく用件だけ言うとさっさと電話は切れてしまった。 とりあえず限られたヒントの「中央広場」「ガーゴイルの像」を目指して歩いていく。 「ほんとにたどり着けるのかな…」 そうぼやいて、エドワードに対する不満を思わず口にしそうだったが、まずは行ってみようと目的地に向かう。 街を歩く。 多くの人が行きかうメインストリートを一歩一歩ハイデリヒは歩く。少し油断すると、他の通行人にぶつかる。夜と昼の狭間で全てが紅く染まる今の時間。自然と歩く人のスピードは早くなっているからだ。一日を終えて、家で待つ人の為に、または大切な人と会うために。そうまるで自分のように。そう周囲の人と自分を照らし合わせていたら、自然に自分の足取りも早くなっていた。 …はやくエドワードさんに会いたいな。 そんな感情が心にわいてきた。一日の終わりに会いたいと思う人がいて、そしてその人に会うために、歩いていける自分。 幸せはこういうものなのかな?些細なことなのに、とても幸せなことのように思えてきた。 人は幸せな気持ちを感じると、顔もほころぶものである。今のハイデリヒの笑顔は傍を通り過ぎるだけの人にも、何かしらの幸せな気分にさせるものだった。 無意識のうちに幸せを振りまいているのに気付かないで歩いていると、目的地近くに着く。 さて、周りを見回すと、一角にシュークリーム店を見つけた。そこから甘いカスタードのにおいが漂う。 「そういえば、最近甘いものなんて食べてないよな。エドワードさん、甘いもの好きだったよな…たまには贅沢してもいいかな?」 この不景気のご時世、お菓子などの『贅沢品』はまだまだ一般には普及していなかった。お菓子の普及として、味を広めようとある貴族のお抱えパティシェだったコックがここに店を構えたのは、半年前。当時は閑古鳥が鳴いていたが、少しずつバイエルン市民に受け入れられてきつつあった。ハイデリヒも噂は聞いていたが、毎日通り過ぎるだけで店をまじまじと見たのははじめてであった。 メニューはシンプルにシュークリーム。今の店の規模ではこれが限界との事を、支払いの時に親父の店主から聞いた。でも、今後みんなが買ってくれるなら、少しずつメニューを増やしていこうとも話してくれた。 戦後のみな不安定な状況の中、その極限ともいえる状況でも、本来人間が持つ尊厳とかゆとりを思い出そうとしている人がいる事をハイデリヒはなんとなく誇りに思った。たかがお菓子ではあるが、それを大切な人に買って帰ろうと、そして一緒に食べようという他者を想う気持ちがあれば。どんなにも人間は穏やかにすごくすことができるのか、たかがお菓子、されどお菓子。人の嗜好はあれども、こんな『美味しいものを』を楽しむことも人生には必要だよなって。そんな事を考えた。 ・・・あれ、『美味しいもの』…? ハイデリヒはふと思い出す。エドワードが言った待ち合わせ場所を。 「なるほどね、『美味しい所』ね…」 そう小声で言って、その店の店頭がある角を曲がる。壁になっている店の側面に、会いたいと思っていた、その人がいた。夕日に照らされて、金の髪が茶色に見える。視線はまっすぐ沈み行く太陽を見ている。真剣にその動きを見逃さないようにまっすぐと。 その姿を見て、なんとなく声をかけるより、どんなものを見るのか、彼の視線にはどんなものが見えるのか、一緒に共有したくなった。そっと邪魔をしないように、隣に同じように壁にもたれかかる。 「遅かったな」 隣に人の気配を感じてエドワードは軽く視線を投げかける。 「お待たせしました」 目をちょっとだけ、細めて視線を返す。 「わかっただろ?『美味しい所』で。」 子供ができばえを自慢するような、そんな瞳をさせている。 「はい、すぐわかりましたよ。それにしてもよく知っていましたね?あまり外出しないあなたが。」 「先日、研究室の帰りにやっぱりこの時間に通ってな。目印になると思ったし…」 今まで夕日を見ていた視線を今度はハイデリヒにまっすぐ向ける。 「ここから見る夕日がまたきれいで。これをお前に見せたかったんだ。」 少しはにかんだような笑顔で、エドワードは続ける。 「この、時代、俺もお前も、毎日生きるのに必死だ。研究費用だって湯水のようにあるわけじゃない。限られた中で、限られた期限で…。空を見る余裕もないよな。お互い…だから。たまにはこんな時間もあっていいかな?って電話を聞いたとき思ったんだよ。…たまには俺たちも人間らしい時間を持った方がいいんじゃないかって?」 ハイデリヒはまじまじとエドワードを見つめる。 「そうですよね…」 偶然とはいえ、同じような気持ちをエドワードが感じてくれていたことにすごく嬉しく思った。お互いを想うその気持ちが、リンクした。 「なんだよ?お前はそう思わないのかよ?」 「い、いえ、そんなこと、むしろ。あなたと同じこと考えていたので本当にびっくりしたんですよ」 反応が鈍いハイデリヒに、文句のひとつをつけようと向き直ったエドワードをハイデリヒは思わず抱きしめる。 「何で?」 あまり抵抗する様子もなく、腕の中でエドワードは質問する。 「なんとなく。今あなたを抱きしめたくなった。」 「…お前は、思ったことはすぐ行動に移すのかよ?」 「…あなた限定でね。」 それだけ言うと、エドワードを体から離す。一瞬だけど、感じられたお互いの体温がいとおしく感じる。 「なんだよ、それだけでよかったのか?」 揶揄するような顔を向ける。 「…まあ、一応人前ですしね。今はこれで我慢しておきます。」 ハイデリヒは余裕のある笑顔を見せる。もちろん余裕なんてないのだけど、たまには見栄を張りたいこともあるのだ。 「エドワードさん、お腹は空いてますか?もしまだもう少し余裕があるなら、広場の噴水でちょっとだけのんびりしませんか?」 ハイデリヒは今買ったシュークリームの箱を鞄から取り出す。 「自分としては、せっかくあなたが僕に見せたいといってくれたこの夕日を、もう少し感じていたいなと思うんですよ・・・・あなたとね。。どうですか?」 ハイデリヒはウィンクをしながら提案する。 「…多少腹は減っているが、そういう相談なら、大歓迎だぜ。あっちにベンチがあるよな?」 二人は、広場に向かって歩き出す。夕日に向かって。でもそれは。 明日また力強く歩く為の、必要な休息な時間。大切な人と過ごす大切な。 おのおのの目的の為に、太陽の下で歩くけど。 太陽が顔を隠せばまた、寄り添う。明日を生きる為に。 その力をお互いから得る為に。 |
| 9月30日 |
| (なんでもありのパラレルワールド。とりあえず、エドが錬金術世界に残ったとして。弟もこっちにいる) 全てが終わった。出会いも別れも。すべて。 それぞれの人が、それぞれの道を歩き出した。エドワードもそのひとり。国家錬金術師としてではなく、一研究者として、軍部の資金援助のもと、錬金術の研究を続けた。公表はされてはいないが、人体錬成を試みたその経験を生かして、医術関連の研究にも携わるようになっていた。 国家錬金術師として、そのまま研究を続けてもという提案もあった。その方が軍部の地位も資金も雲泥の差だったからだ。 −戦争に借り出される可能性が少しでもあるならもう国家錬金術師でいたくない…戦争がいやだっていうんじゃなくて…その間に大切な人と別れるのは…もういやだ。俺はもう二度と傍を離れたくない…− そう言って、エドはあっさりと銀時計を返還した。世にいる錬金術師が切望する象徴である銀時計をあっさりと手放すのは、エドが欲しいものを手に入れた、その証拠であろう。大切なものは手に入れた。 エドが研究所を歩いていると、開け放たれたその扉が目にはいる。 (大佐…おっともう准将だっけ?あいつの部屋じゃん…) 例の騒動のあと、ロイ・マスタングは、事態の収束に多大なる貢献をしたということで、元の大佐の階級よりさらに昇進した、准将の地位を与えられた。もともと伍長への降格自体が、一時的な措置であったのに北方行きを志願したのはロイ自身だったからだ。その当人がセントラルに戻ると決めた時点で、元の階級は約束されていたのだった。 (部屋開けっ放しにして…出かけたのかよ?無用心だな…?) 開けている扉を親切心で閉めてやろうと、ノブに手を伸ばした時に奥に横たわる人影を見つけた。木漏れ日が差し込み、細くあいた窓から吹き込む小さな風で薄手のカーテンが揺れている。そのそよ風が心地よく部屋の主が窓際のソファーで心地よい眠りにつくのを、優しく見守っている。 その光景を見て、エドはなんとなく今までにない幸せな時間を感じた。あのロイがこんなにものんびりできる時間が…今のここにはある。それがつかの間の時間であっても。確実に今は。 なるべく音を立てないように、近寄る。 以前のロイであったら、どんなに熟睡しているように見えても、部屋に入った時点でその気配を察して飛び起きていたが、平穏な時間の油断からか?それとも自分だからか?薄目を開けたのはあと数歩までに近づいたときであった。 「だ、誰だ……鋼の?」 寝ぼけた顔を隠そうとせずに、右手で目をこすり、半身を起こす。 「その名前は返上したって…何度も言ってるだろ?」 エドワードは腰に左手を当てて答える。 「一度つけられたふたつ名は、もう二度と使われることはない…銀時計を返上しても、その名は永遠にお前のものだよ。」 ゆったりとソファーの空いたスペースに腰を下ろすエドの髪を弄りながら話す。 「・・・・そうだっけな」 そっとつぶやく。それは「鋼の錬金術師」として生きてきたその年月を記憶の中でなぞるような、そんな呟きだった。 「いつまでこの平穏な時間が続くかどうかわからないが…私はこの時間の為に…まだ努力しようと思うよ…今までとは形は違うが…協力してくれ。全ての人を幸せに…なんておこがましいことは言わない…でも私は、一握りかもしれないが、わたしが知っている人々には幸せになって欲しい、そうおもうよ。その為に今私はここにいる…」 「准将…」 失われた左目を保護する眼帯をそっとおさえながら、小さくつぶやく。 何を言うわけではなく、静かな時間が流れる。すると、エドワードの肩に押し当てられる重み。 ふと見るとロイが再びエドの肩を枕に寝入ってしまっていた。仕事量は決して少なくはないのだが、最近のロイはよく寝るようになった。今まで、不安で眠れなかった時間を取り戻すかのように。もちろん限られた人の前ではあるが、自分もその中に含まれているのは、なにやらくすぐったい感じがする。上を目指す彼の、安らぎのひとつではあるのか…。 「また寝ちまったのかよ…?」 困った顔だけど、エドの目は笑っている。 「仕方ねえな…俺も眠いや…」 触れる体が、布越しでも暖かく感じる。その体温が確かにそこに彼が隣にいる事を実感させる。 人は寝ている人を見ると、眠くなるものではあるが、ロイの寝顔も例外ではない。エドも我慢を放棄してそっと目を閉じる。 「にいさーーん」 昼過ぎに研究室に資料を置きに行っただけのはずの兄が、夕方になっても帰ってこないので心配して探しに来たアル。軍の入室管理帳によるとまだ退出してないとの事なので、研究室から執務室を探して歩いていた。 「マスタング准将なら知っているかな…?」 彼の執務室に足を向けたアルが見たものは、ソファーで仲良く居眠りする二人の姿だった。 「ふたりとも!何してるのさ??兄さんはまったく帰ってこないし、准将も准将ですよ!仕事はどうしたんですか??」 怒鳴り声というより、最近トンと感じることのなかった殺気で二人は飛び起き、声の発生源を探し、そこにアルを見つける。 別に二人で居眠りしてただけ、それだけだったのだが、アルにとっては言いようもない感情が爆発した。あえて言うならそれは嫉妬というのだろうけど、なんとなく二人仲良くしているのが気に食わなかったのである。 「ア、アル…す、すまんすぐ帰るって言ったのに…遅くなって…!ど、どうしてそんなに怒ってるんだよ…?」 昼ぐらいからだから、数時間は熟睡していたはずであるが、その殺気に一瞬で目が覚めたエドはアルに必死で弁明する。 「知らないよ!!どうして怒ってるかなんて!兄さんの馬鹿〜!」 理論が通ってない、アルも自分自身何を言ってるのかわかってない様子である… 「…という訳でマスタング准将!兄さんを連れて帰ります!」 エドの右手を引き寄せる、兄を抱きとめる。その目は威嚇する犬のように思いっきりロイを睨んでいる。 「…ご自由に」 微笑をたたえつつ余裕の表情で返す。 「さあ、帰るよ、兄さん!」 「お、おい!」 エドは問答無用で口答えする間もなく、引きずられるように、部屋を後にする。 「また来いよ、鋼の。」 ひらひらと手を二人に振る。 「もう二度ときません!兄さんはこの部屋には!」 エドの変わりにアルが答える。 「…幼いなあ…あの二人は。」 思わず苦笑してしまうロイだった。家で寝るよりも熟眠した手ごたえをえたロイは、再び執務机に向かう。 |
| 9月28日 |
| 「神を継ぐ少女」 ウィンリィ 「絶対に帰ってくるって…!約束して!」 それはしていい約束なのか?悪いのかそれは、言ったウィンリィ本人にもわからなかった。 いつドアが開くのか、今こそ、その扉が開いて、3人が帰ってくるかと、何度も何度も待って、待って、ずっと待って。 何回も、ふとした音に希望し、それがただの物音であったことに落胆する… そんな事を数え切れないほど繰り返した。今回もまた気のせいだ…。でも振り向かずにはいられない。今度こそは…期待してしまう。 そこには、いつもと違った光が…差し込んでいた… 振り向くと閉じられていた、その教会の扉が開いている。逆光に二つの影。 「エド、アル!!」 ようやく…帰ってきた!今度こそは…幻でも気のせいでもないのね! よかった無事で…!そう言おうと思った。何度も何度も練習した…はずだったのに… 「遅ーーーーーーーい!一体いつまで待たせるのよ!」 口から出た言葉はこんな感じ。自分でも素直じゃないと思う。でもでも、待つだけの辛さに比べたら。これくらい許してよ!! 「ご、ごめん!ウィンリィ…!」 「いてえぞ!帰ってきていきなり殴ることはないだろう!!」 案の定、アルからは謝罪の言葉、エドからは非難の言葉。でもでも。どんな言葉でも返ってくる言葉が嬉しい。ひとりで寂しくノルンと待つのに比べたら。手の届くところに戻ってきてくれた。 しかし。それはつかの間の喜びだった。いるはずの、付き合いは短いのに、いつの間にかかけがえのない友達、もうひとりの「仲間」がいなかった。 敵に捕まった…取り戻しにいってくる…エドはそう言った。 何で、ソフィが敵に捕まるのをすごすごとみていたのよ!一瞬そう怒鳴ろうと思った。 ソフィとは教会でエドとアルを待っている間、いろいろ話した。姉妹のように思えた。だからこそ、全てが終わったらリゼンブールで過ごそうって、社交辞令じゃなくて本当に来て欲しいから、まだまだ一緒に居たかったの。私が。 二人の表情を見ると…それは言ってはいけないことだった。だって、二人が黙って見過ごすわけはない。仲間が連れされられるくらいなら、自分を差し出す、相手の傷は自分の傷より深くその心に刻み込んでしまう、そんな性格であることは、幼馴染である自分がよくわかっていた。 こんな時に、黙って見守ることしかできない自分が悔しい…。 自分にできることは、やっぱり見守ることしかないのだ。でも。それは、この二人にとっては必要なこと。私だからできること。今の私にしかできない事。 「ウィンリィ…万が一…万が一だぞ…?俺たちが戻ってこなくて…ここが危険になったら…俺たちを待たずに…逃げろ…!」 かけがえのない仲間を取り戻すべく、突如出現したあの塔に、赴く直前、エドはそう私に言った。私の目を見ずに。 確かにそれは、正しい発言だ。優しい兄弟は自分の身を案じてくれている。危険を及ばないように、逃げろといってくれる。そうすれば、私は何かあったら帰れるだろう。 「いやだ!絶対ここで待つ!あんたたちが帰ってくるのをここで待つ!逃げてなんかやらない!」 涙が出そうになるのを…必死でこらえる。今泣くな、今、泣いたら二人が出かけられなくなる。笑って見送るんだ、ウィンリィ。何度も何度も心に言い聞かせる。 「ウィンリィ…」 ようやく自分に視線を向ける。困ったようないつもの優しい笑顔を。鎧のはずのアルも光の加減か、微笑んで見える。 「ここであんたたちを待つ!絶対に帰ってくるって…!約束して!」 再度自分に言い聞かせるように、強くつぶやく。 あんたたちは、危なっかしいんだから。私が逃げただろう…?って事を逃げ道にさせてなんかやらない。弱気になるチャンスを与えてなんてやらない。いつまでも強気で、あいつのところまで帰るんだ、って何処までもあがきなさい!絶対に帰ってきなさい!ここで待ってるから。ソフィを連れて。 「…わかった…神だかなんだか知らないけど、さっさと倒して、ソフィを取り戻してくるぜ!」 そのまっすぐな金の瞳に、光が宿り、はにかんだように笑う… 「うん!いってらっしゃい!」 右手でエドの、左手でアルの背中を…押し出す! ふたりは、一歩踏み出した。決して自分を振り向くことなく。 それでいい。また会えるんだから、振り向く必要なんてない。また会えるんだから。 私はここで待つ。希望を持って待つことが私にできる、私にしかできない戦い。 |
| 9月27日 |
| 「神を継ぐ少女」 ロイ・マスタング初登場シーン (…俺は…ここで終わるのか…?) 視界が真紅に染まった時、彼は今まで考えることもなかった自分の最期を予感した。 (いままで、どんなことがあっても…最期を考えた時はなかったのに…) イシュバールでの惨劇の間、誰もが死と隣り合わせ出会ったあの時間、それでも、自分だけは無事であろう、そんな漠然とした実感があった。そして、それは実現となった。「死」とは与えるものであって、与えられるものではない、そう信じていた。今までは。 (焔の錬金術師と言われた…この俺が、焔で死ぬとはな…) なんて滑稽だ…と自嘲する。今までこれで人に引導を渡していたのに…自分がそうなるとは…。今まで奪ってきた命への報いか…? (…それもいいのかな…) もうまともに思い出すこともできないはずなのに、自分が摘み取ってきた人々の顔が網膜に浮かぶ。 (ふ、因果応報か…) そんな言葉がよぎる…。高みを望んだ、それが不相応だったのか。これがその証明なのか… かたり、 今まで自分の中で崩れることがないと思っていた、何かが崩れる音が聞こえた。 今の自分では、煉獄のゼルギウスと名乗ったあいつの仮面を崩すだけしかできなかった…その仮面が崩れるように…壊れていく自分の中の何か。 人間以上の何かの力が、そいつに味方している、だから俺の力が及ばなくてもいい、そんなことはただの言い訳にしか過ぎない、負けは負けだ。万策は尽きた。俺が出しうる全力の焔をあっさりと握りつぶした。悪あがきをするには、力の差は歴然としていた。 (俺はなんて無力なんだ…、結局俺の手は…血に染まっただけで何もできなかった…) 無意識に右手で左肩を掴む。偶然にもそれは祈りの姿になったのか。 (…すまん…俺もお前のところに行くぞ…!) 屋上に陣取るゼルギウス。その姿は遠くて見えないはずなのに…、そいつが作り上げる炎が見る見るうちに巨大になって自分に引き寄せられるように向かってくる。 (ヒューズ!) 最期の最期に思い浮かぶのは…やっぱりお前の顔だったよ…そう、いったらお前はどんな顔をするかな… 自分の力も、過去も、そして、最期を。全てを受け入れた。かの人の顔を思い出すがごとくに、目を閉じようとしたその瞬間。目の前に自分の前にたちはだかる、二つの影。 全てをかき消す、紅き閃光ののち、目の前の影は形を成す。 「鋼の…」 助かったのか…?でもお前に助けられるとはな…。 すまん、お前のところに行くのはもう少し先になりそうだ… もう、少し待てるか? 右手をそっと降ろし、立ち上がる。 まだ俺は、戦える。いや、戦う。どんな形でも命がまだあるなら。 どんなに惨めでも、生き抜いてみせる。この命がある限り。 |
| 9月26日 |
| 「おい、アルフォンス…いい加減に寝ろよ!」 研究用の図書を大学に取り行っていたエドワードが、アパートメントに帰ってきたときに見たのは、家を出た時と同じ格好でいるアルフォンス・ハイデリヒの姿だった。 「…あ、もうそんな時間ですか…?気づかなかった…」 かけられた声にふと顔を上げたアルフォンスの眼の下には、はっきりとわかるクマが浮かび上がっていた。 「お前昨日も徹夜してただろうが!!」 やや怒気を含んではいるが、心配そうな瞳をしながら近づく。 「…大丈夫ですよ、好きなことなんですから…やりたいことなんですよ…僕が…。」 疲れているはずなのに…眼は優しく笑いながら。そんな微笑をエドワードは痛々しくて見ていられなかった…。 何で、そんなに頑張るんだよ…?どうしてだよ?喉の奥にこみ上げてくる言葉。 「あと少しなんですよ…あと少しで…、ロケットの装着に耐えうる液体燃料の実験の確証実験が終わるんですよ…!」 でも、それは一分、一秒を争うものなのかよ、お前の体が壊れちまう!以前、そう何度も言った。でもアルフォンスは聞き入れなかった…。まるで何かにとり憑かれたのような、生き急ぐかのような彼の姿に…何もできない自分を何度も目の当たりにした。 ロケットを作りたいだけ、そう彼は言った。17歳の身で、いくつかの偶然も含んではいるが、工場を得る為のチャンスが眼の前に転がっているのだ。 ある軍の関係者の方が、自分たちの確証テストの結果次第では、工場を一つ任せてくれるんだ、そう笑って話してくれた。 だからこそ、強引に止める事ができない自分がここにいる。 また自分に背を向けて、デスクの紙面に向かう彼を見ると、過去の自分を思い出す。 体を取り戻すために、すぐそこにチャンスがぶら下がっていたら。自己を犠牲にしてまでもチャンスを掴みたいと願っただろう。 だからこそ、とめることができない自分がもどかしい。 でも。見ているのもつらい自分。 エドワードはその背中にそっと額を押し付けた。 「…お前の願いは…わかってる。これ以上は止めない…お前の夢だもんな…でも俺が、心配しているのだけは、忘れんなよ…?ひと段落着いたら…またご飯食べような、一緒に…。」 エドワードはそれだけ言うと、軽く両手で広い背中を軽く抱きしめて耳元で呟いた。 「エドワードさん…」 アルフォンスが振り向いたのは、その手が離れ、後姿が次の間に消えていったその時であった。 耳の中に残ったその言葉と、背中に残るやさしいぬくもりに思わず執筆の手を止めてしまう…。 その余韻に、数分浸りつつ、手や首の運動をして少し気分をリフレッシュしてから、またペンを握った。 「あなたって人は…」 さっきとは違い、心の底から微笑んでいるアルフォンスの姿。 「これでさらに頑張れちゃうかもね?」 ちょっと元気になった彼は、心意気も新たに研究を続けるのであった…。 |
| 9月22日 |
| 神を継ぐ少女 洗濯石鹸ネタ 「…なんでこんなもんが、こんなところに落ちてるんだよ?」 すでにヴェルザに攻撃を受け、封鎖されたヴァルドラの地下鉄構内にそれは落ちていた。 「うーん?あのお母さんが買い物して…って言うのは無理があるしね?」 さっき以前助けた親子と無事に再会を果たしたが…ここまで逃げてくるのに、これを肌身離さずもっていた? 「ほんと、訳わかんね〜!!」 「まあ、いいじゃん、とりあえずもって帰ろうよ。これ。ウィンリィとソフィにあげればいいよ。」 「…そうだな」 地裂のゴドー戦をなんとかクリアして、二つ目のオベリスクを封印して戻ってきた二人。 「おかえり、エド、アル。大丈夫だった?」 それを優しく迎え入れるウィンリィとソフィ。 (やっぱり、どんな時でも迎えてくれる顔があるのは…いいもんだな…) 二人の女の子特有の柔らかな笑顔を見ると、ふと心が温かくなる。 「二つ目のオベリスクを封印してきた…でもますます敵も強くなってくるなあ〜!」 「…!」 その言葉を聞いてソフィはうつむいてしまう… 「兄さん!!ソフィ!大丈夫だよ、これでも兄さん頑丈だし、僕だって兄さんに錬成してもらえれば何度だって敵に立ち向かえるんだから!今までの苦労に比べれば、こんなのへの河童だよ!」 自分の運命の歯車に巻き込んでしまった…ソフィは何度もそんな顔をする… 「ソフィ、気にすんなって!俺たちこうやってまた帰って来れただろ?あ、ソフィ、今回こんなもの拾ったんだ!プレゼントになるかわからないけど…?」 エドワードは先ほど拾ったアイテムをソフィに手渡す。 「…石鹸…?」 「…ごめん、プレゼント…になんねえよな…?」 失敗したか?という表情でアルと視線を合わせる。 「…ぷっ。おかしい、エドワードったら。こんなのプレゼントにするなんて!」 むしろ、あまりにも不似合いなそのアイテムは愉快だったらしい。 「…そ、そうか??」 「ありがとう、大切に…?って言うのはおかしいけどちゃんと使わせてもらうね。」 ソフィは、自分を迎えてくれた時のような柔らかな笑顔だった。 「じゃあ、ソフィ、もらったんだから使おうよ!ちょうどいいし。」 ウィンリィは石鹸をソフィの手の平から受け取る。 「そうね!有効活用しなきゃ!」 「ええと、じゃあ、この奥にあった寝室のシーツと…、教壇のカバーもね。ああ、それと…!」 「…確かにあれも洗いたくなってくる…?」 ソフィとウィンリィの視線の先には、戦いを終えて長いすで眠りこけるエドワード。なにやら、目にあやしい光が…? 「「さーーて、脱がすぞ〜!!」」 二人そろって、怪しい気配漂う中にもかかわらず、起きる気配のないエドワードに向かっていく。 「えええ?な、何するのさ?」 とその行動の一部始終を見ていたアルは慌てて二人を止めようとする。 「何って…?服を洗うのよ〜?」 ウインリィは異様に目を輝かせながら上着に手をかける。 「絶対駄目ーーーーーー!!」 突然アルが声を荒げて、エドの服に手をかけていた二人に割ってはいる。 「何よ?アル。あんたも参加したいの?」 ウインリィはにっこりと微笑む。 「そりゃあ…ってちーーーがーーーう!」 「違うって何が…?」 今度はソフィの目が座っている… こ、怖い…とかんじつつも怖気ずに反論する 「と、年頃の女の子が、な、何してるのさ…?」 「えー、いいじゃん楽しいわよ?」 「楽しいって…?な、なに言ってるの?こんなこと楽しんじゃ駄目だよ!女の子なんだから…!」 「男の子ならいいの・・・?」 ソフィがにっこりと再度微笑む。 「それは…ってそんな問題じゃない〜!」 思わず、そうだよって答えそうになったが…慌ててとどまる。 「とにかく!!兄さんの服を脱がすのは…僕がやるから!!二人はあっち行ってて!」 えーーー!と不平不満を連発する二人を強引に別室に押しやる。 「…まったく…いまどきの女の子って…!でも兄さんの服を脱がすのは!僕だけだ!!」 そういいながらも、いざ脱がせるとなると…ためらう弟… 「で、でも…ここで脱がさないと…!ウインリィたちが…また…!」 照れと嫉妬心と秤にかけて。何とか気持ちの整理をつけて、服に手をかけるも… 「・・・・・・・・・・・・・・・・」 手が動かない…なんでこんなに色っぽいんだよ…?と口に出しては言わないが、アルは常々思う。 そんな弟の迷いもわからずに、すやすやと寝息を立てる兄を見てると、次第に何故だか怒りが… 「何でこんなにも自分ばっかり、照れてなきゃいけないのさ!!」 その勢いで、一気に脱がそうと…するもやっぱり動かない。ちょっと身じろぎする時に見え隠れする鎖骨のラインが…アルを刺激する。 「あーーーーーー、もう!」 できるだけ見ないように、でもエドを起こさないように、微妙な綱渡りをしながら一枚一枚脱がして… 「アル〜。」 そんな気持ちを知ってかしらずか…、またなんとも寝言を… 「あなたって人は…」 ため息をつくアル。 いつまでこんな生活続くのかな…僕の体…早く取り戻したい… 兄さんにちゃんと自分の手で触れたいな… 切実に想う弟。その苦悩を兄はまったく知らない… |
| 9月19日 |
| エドの寝起き ハイデリヒバージョン 「むにゃ…キスしてくれたら起きる…」 ハイデリヒは、今地震がおきた方がよっぽど冷静に対応できるだろう、って思うほど驚いた。 「はい…?」 思わず気持ちよさそうに眠るエドワードをまじまじと見下ろす。あーあ、よだれまでたらして、本当に熟睡している、いや、今夢で見ているのかな… どんな夢を見ているのか…?どうして、その寝言になったのか…?本当は今にでもたたき起こして夢の内容を聞き出したい衝動に駆られる。 (あなたは今一体どんな夢を見ているんですか…?その夢には僕はいますか…?) 聞きたいけど、聞けない。 (あなたの中に僕はいますか…?) 疑問符が次々と心の中に浮かんでくる。 その頬に触れたい、今まで我慢していた想いも同時に沸きあがってくる。 (あなたが…自分で言ったんですよ…?)それが寝言でも…と自分に理由をつけて、手を伸ばす。 その手が届くか届かないかその瞬間 「クシュ…ッ」 突然のくしゃみ。その音にハイデリヒは我にかえった。 「危ない、危ない…」 と、手を引っ込める。 まったく…寝言に惑わされて、夢の中の誰かに嫉妬してしまうなんて。途中で彼が気付いたらどんなことになるか、知れたことじゃない。まったくよかった途中でやめて。 本当は起こしに来たのだが、このまま動揺した気持ちで顔をあわせるのも辛い。昨日聞いたエドワードの今日の予定を思い出し、今起こさなければいけない用事ではない事を確認してから、そっと部屋を出る。 「おやすみなさい、エドワードさん、今度は僕の夢を見てね。」 そうハイデリヒは言い残した。 (おまけ) 部屋を出て行く気配を感じ取って、エドワードはベッドからむくっと起き上がる。 「甲斐性なし…!!」 と、毛布を床にたたきつける。実は、寝言をつぶやいたときに、同時に人の気配がしたので目が覚めたのであるがその人物が夢に出ていたハイデリヒであったので、思わず起きられなくて狸寝入りを決め込んだのだが…。その後ハイデリヒが自分を見下ろし、そして… 「確かに…その瞬間に思わずくしゃみをしてしまったのは…俺だけどよ…」 愚痴愚痴とひとり言を続ける。 「だからって、あれで止めるなよ!」 夢の中の自分は、驚くほど積極的で。いつも素直になれない自分とは対照的だった。 「俺が…あんなことまで言ったんだから…」 要するに。無意識とはいえ、上げ膳を整えてしまった自分を食ってくれなかった彼に逆切れしていたのだった。 「もう、知らん!」 目はすっかり覚めてはいたが、部屋を出て行く気になれず、布団をかぶりなおして再度ふて寝を決め込む。 「あ、エドワードさん。おはようございます」 数時間後、出かけなければいけない時間タイムリミットぎりぎりに起きてきたエドワードにいつもの笑みで声をかけるも、彼はあっさり無視して出かけてしまう。 「…え、エドワードさん…やっぱりさっきの事気付いて、怒ってるのかな…?」 何処までもすれ違う、二人の想い。 想うからこそすれ違ってしまうのではあるが。 その想いが重なり合うのはいつになることやら。それは偶然の神のぞ知る?のか? |
| 9月17日 |
| 寝起きのエド アル(弟)バージョン **** 「むにゃ…キスしてくれたら起きる…」 いつまでたっても起きてこないエドワードを起こしに来た弟アルが聞いた台詞。 は…?聞き間違いか?と思わず自分の耳を疑った。改めてまじまじと兄を見下ろす。しばし考える。 その間もはだけたしゃつの下からさり気に見える肌なんかが何かと気になってしまう。 「そういうことなら」と一言つぶやいて、毛布を引っぺがし、隣にもぐりこむ。 「…さぶっ」 突然の冷気にようやく目を開けたエドワードが薄目を開けたときには、弟の顔が目の前にあった 「ア、アル??どうしたんだよ?」 「兄さん!覚えてないの?寝ぼけているなんて…昨日の事を忘れたなんて!!酷い!」 アルは大げさに驚いてみせる。 何がなんだかわかってないエドワードは寝起きの頭をフル回転させるが、どうも記憶にない。 「お、俺なんかしたのか…?」 「ほ、ほ、本当に覚えてないの?」 何もないだから、覚えてなくて当然なのだが、すっかりアルの演技に騙されている。 「ご、ごめん…」 「兄さんなんて!」 と嘘泣きをして部屋を飛び出す。 偽りで流した涙を袖で拭いたアルはぺろっと舌を出す。 (やりすぎたかな…でも僕の気持ちを知った上であんな寝言いう、兄さんがいけないんだよ…!しかもあんなカッコでさ…) つまり、無意識とはいえ自分を誘うような事を、結果的に自分の気持ちを試すようなエドワードについ仕返しをしたのだった。 |
| 9月13日 |
| 「なにそんなに拗ねてるのさ?」 拗ねたような表情をあからさまにこちらに向けるエドワードに、自分が一体何をしたのさ?とばかりに多少なりとも不快な思いを持って訊ねる。 「…」 一瞥しただけで、ぷいっとあちら側を向いてしまった。 「なんなの?兄さんは?何ご機嫌斜めなのさ?」 そう、再度訊ねても答えないエドワードの正面に回り込む。 眉間に皺を寄せて睨みつけるエドとちょうど正面に視線があう。 「…やっぱり…」 何がやっぱりなの?と首をかしげていると 「お前、いつの間に背が伸びた!」 「…は?」 要するに、エドワードは多少なりともあった身長差がなくなっていた、エドにとっては重大な事実に気付いてしまったのである。 「俺に黙って何をした?どうしてそんなに身長がいつの間にか高くなった??」 「…何をしたって…!何もしてないって…痛っつ」 左手でパンチを繰り出すエドに対して必死に防戦するアルであるが、ギリギリ一杯で避ける。 「兄に黙って身長が高くなるのは、いけないって教わらなかったのか?」 もはや言いがかりである。 「兄さん、誰がそんな事決めたのさ?」 ついに足技まで繰り出そうとするエドに対して、反論しつつ、反撃するのは難しくなってきた。 「五月蝿い!!」 「それはいくら僕相手でも!」 ついに、左足の回し蹴りが炸裂しそうになったので、思わす手加減ができずにその足を捉えて、エドの重心を崩させ受身を取らせる。 「…っ!」 ふう、とため息をつき、ちょっとやりすぎたかな?とエドを見下ろす。 「兄さんちょっとは冷静になってよ!」 その言葉に多少なりとも自暴自棄になっていた自分に気付き、アルを見上げた。 「ごめん…」 自分に非があってもあまり謝らないエドワードが、頭を下げるときは本当に反省している事を知っているアルは優しく手を差し伸べ立つのを促す。 「ごめんね、兄さん。大きくなっちゃって。」 嫌味とも取られかねないが、思わず言ってしまった。 「…」 答えないエド。 「…特に何をしていたわけじゃないんだけどね。でも僕、嬉しいんだ…。身長が伸びたってことではなくて、それによって兄さんに近づけたようで…。離れていた2年間…記憶も取り戻したけど…形になるものじゃないじゃない?」 ふと語りだすアルに、ようやく顔の緊張を緩めた表情になる。 「…これでちょっとは離れた歳の差が近づく感じがした…でも兄さんにとっては嬉しくないことなんだよね、それなのに、喜んじゃってごめんね。兄さん。」 照れと謝罪などが混在した複雑な表情を浮かべるアルを見ると、エドはそっと抱きしめる。 「そうだよな…俺は…まだ成長期だ!これから伸びるから大丈夫だ!」 アルの肩に顎を乗せそっと囁く。 「兄さん…」 同じ身長になった兄弟は改めて同じ視線で見つめあい、くすっと笑う。 その時アルはこんな事を思っていた (兄さん…負けないよ?これから僕はもっと背が高くなるかもしれないけど…その時には言わせてね。「僕が兄さんを守るって」まだ、これじゃ言えないよね。) |
| 9月12日 なんとなく、強気なエドが書きたかったの。 |
| 「な、なんですか?準備が出来ないじゃないですか?危ないですよ!」 夕食の準備をしていると、エドワードが背後から耳に吐息を吹きかけてきたので驚き思わず包丁を落としそうになる。 「ちょっと、イタズラ。」 悪びれもせずに、エドワードは笑みを浮かべる。 「い、いきなりなんですか?」 「…いきなりじゃなければ、いいのかよ…?」 さらに顔を近づけて耳元で囁く。 「予告をしても駄目です!」 ハイデヒリはそれだけいうので精一杯という感じで顔を真っ赤にしてエドワードから逃れようとするが、気付くと彼の両手は自分を挟むようにキッチンの縁に。 逃げられないハイデリヒは観念したように身をすくめる。 「…冗談だよ、早く準備しろよ…腹減った。」 エドワードは、あっさりそういうと、リビングに身を翻していく。 「…え?」 そのあっけなさに、逆に驚いてしまうハイデリヒ。その表情を見透かしたのようにエドワードは振り向いて一言。 「食事のあとな。」 何が食事のあとなんだろう?と思いつつ同時に期待してしまった自分の心を見透かされそうになったので慌てて下を向き取り落としそうになった包丁を持ち直し食事の準備を続ける。 |
| 9月11日 なんとなく…へたれヒリが書きたかったの。多分。 |
| シャンバラから来たエドワードを執拗に狙う国家主義労働党の一派が、二人で歩いているところに襲ってきた。 「僕のことはどう傷つけられたってかまいません!でも…エドワードさんを傷つけるものは、許しません!」 ハイデリヒは、エドワードを庇うように間に立ちふさがる。 「僕が守るんだ…!っごほ。」 「お前!発作が!」 目の前で崩れ落ちるハイデリヒをすんでのところで抱きとめる。その間に、男たちは一歩一歩近づいてくる。 「…逃げるぞ!」 エドワードはハイデリヒを腕を取り取り囲む一党から脱兎のごとく逃げ出す。 「お前なあ…啖呵を切るのはいいけど、それなりに決める時は決めろよ…!」 街角のマンションの狭間に逃げ込めた2人。エドワードは息を整えつつ文句を言う。 「だって、僕があなたを守りたいんだ…」 座り込んではいるが、発作がおさまり、会話が出来るようになったハイデリヒはやや上目遣いでつぶやく。 咳き込んだせいで潤みがちになった瞳を向けられて、エドワードはやや困った顔。 「…わかったよ、守られてやるけど、俺もお前を守ってやるからな。お互い様だ。」 左手でハイデリヒのつむじ辺りをぽんぽんとたたく。 「帰ろうぜ。俺たちの住む家に。」 「…はい」 差し出された左手を取りハイデリヒは立ち上がる。 |
| 9月10日 モンゴル滞在中に思いついたネタです。星新一さんの小説を読んだので、うまく読者さんをミスリードさせることができるか挑戦したんですが? |
| 「痛てえ…」 エドワードは苦痛に顔をゆがめる。 「まったく、自業自得ですよ。入れた後に無茶して勝手に動くからですよ!」 ハイデリヒは、少しさげすんだような瞳を向ける 「だって、我慢できなかったんだよ…早くしたかったんだよ。わかれよ、いい加減にお前も…?」 「ちゃんと慣らしてから入れれば、それから動けば痛くないんだって何度もいってるじゃないですか?」 忠告は何度もしているじゃないですか?って目が語っている。 「…だって」 「だってもないでしょう!本来はちゃんと入るようにはなってますが、慣らしが大切なんですから!入れてそのまま勝手に動かないでください!あとで痛い思いをするのはあなたなんですよ!」 「…」 二の句に継げられないエドワードにハイデリヒは続ける。 「見せてください!大きくなってるでしょ?」 「…ヤダ…」 「僕が処理してあげますから!さっさと脱ぐ!」 ハイデリヒが指の関節を鳴らせてエドワードに迫ってくる。 「…やめろ!じ、自分で出来る!」 「そういってもうそんなに大きくなってるじゃないですか?さっさと脱ぐ!」 「・・・!」 「ほら、こんなに足のマメが大きくなってるじゃないですか!ああ、もうこんなに!4個も出来てるじゃないですか?あれだけ新しい靴を履くときは、ちゃんと足の形に靴を慣らしてからきちんと足を入れれば、マメなんて出来ないんですから!慣らしが終わるまで、あんなに長距離をいきなり動き回るなって言ってるでしょ?新しい靴が楽しくって歩き回るなんて…だから子供だっていわれるんですからね!わかってるんですか?」 足をつかんで靴下をあっという間に脱がしたハイデリヒはあきれた顔で続ける。 「これなら…マメはつぶれてないですから、消毒はいりませんけど、破れないように保護しときますからね!」 「マメマメ言うな…」 エドワードはこっそりとつぶやくが、ハイデリヒには聞こえていない。 「なんですか??ハイ、出来ました!履かせてあげますからそこに座る!」 すっかり命令口調で、頭にくるのだが、なんとなく従ってしまう。 丁寧に靴下を履かせると、今まで履きなれていた靴を履かせようとするちょっと前に、ハイデリヒは靴下を少しさげて口付け、元の位置に戻す。その瞬間に見えた、紅い印。 「お、お前汚い!」 「そんな事ないですよ、でも次に同じ事やったらもっと目立つところにつけますよ。ハイ、忘れない為のおまじない」 「…二度とやらない…」 反省とも、照れとも取れる微妙な表情で一言つぶやく。 「そうしてくれると僕の心配も少なくなるので助かります。隠そうとしたって、歩き方でわかりますからね…」 そっと丁寧な手つきで靴を履かせながら伝える。優しく。そっと。 |
| 8月31日 夏休み最終日ということで(いや、私は夏休みなんて関係ない年頃ですよ) |
| 「何でここで迷うんだよ?さっさと言えばいいじゃないかよ?」 国語の教科書の中のひとつの作品で、異国の少女が親に寂しいと言いたいけど言えない…そんな心の描写を描いた作品を読んで、エドワードは呟いた。 「何でって、言いたくたって言えないことがあるでしょ?」 ひとつ年下ではあるが、少人数の田舎の学校なので課題は一緒だったアルフォンスは隣で、宿題をやっていたがそのエドワードの問いに、あっさりと回答した。 「何で言いたいのに言えないんだ?」 1+1=2はどうしてだ?といわんばかりの明確な答えを求めているエドワードにとっては、言いたいことがあるのに言わないというか、言わないというのは不思議だったのである。 「そんな事言ったって…兄さんにはないの?そんな事?」 「ない」 即答する。思ったことは言う。目標とした事を出来ないかもしれないとか、自分に対する不安なんてまったく持たずにひたすら努力する才能を持ったエドワードが自分の兄である事を、誇らしくもあり…少々羨ましくもある。時々まぶしすぎると思うことも。 「…兄さんにもそのうちわかるときがあるんじゃないの?」 具体的な解決を求めているエドワードだがわざと矛先をずらす。 「そんなもんか?」 「そんなもんだよ。たとえば好きな子が出来た時とかね。」 「…俺は言う時はいうぞ?」 「本当に好きで大事な相手なら、簡単に言えないって。本当に大事な相手ならね。」 ちょっと困った顔でアルフォンスが答えるので、思わず訊いてみた。 「お前にもいるのか?言いたくても言えない相手って。」 「…いるよ。」 いつもとは違う、優しさをたたえた優しい目をして答える。自分より年下のはずなのに、そんな表情をするのかとエドワードは心の奥で傷む何かを感じる。 「誰だよ?そいつは?」 アルフォンスが誰を好きになろうかなんて、それは自由だ。追求なんて。そんな事したくないのに、つい出てしまったその言葉。 「内緒」 そう答えたアルフォンスに、エドワードは落胆と確かに安堵感の両方を感じた。まだアルフォンスの一番でいられる自分に対して。 「僕、ちょっと用事を思い出した。宿題進めてね、兄さん。明日から学校なんだからね。」 そう一言残すと、アルフォンスは部屋から出て行く。 「まったく…目の前にいるって…」 エドワードから充分に離れたのを確認すると、アルフォンスはため息をつく。 「兄さんが僕の気持ちに気付くのは一体いつになるのかな…はあ。」 ため息をふたつ。 幼いながらも、ちゃんとしたこの気持ちは。単の兄を慕う気持ち出ないのを自覚している弟。でもそれは言ってはいけないこと。言いたくても言えないその相手を目の前に、それを言われるとちょっと辛い。我ながら厄介な相手を好きになったな…と思いつつ、諦める気なんてさらさらないアルフォンスであった。 |
